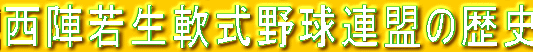 3
3
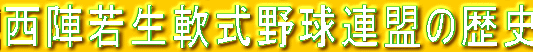 3
3
■6年目 昭和40年(1965年) 参加10チーム
よちよち歩きの西陣若生軟式野球連盟も、ようやくひとり歩きができるようになった6年目、
スリッカーズチームが参加してきた。初参加 初優勝は特に珍しいことではないが、この年はスリッカ
ーズが初参加初優勝。以来、今日までヤローズに次いで参加し続けている強力チームである。
スリッカーズの参加があったものの 若生リーグは10チームに減り、3回総当りとなった。
このころから若生リーグへの愛着を深める人たちが増え、現在への基礎が整ったようだ。
そのひとりが現会長の崎田四郎である。
■7年目 昭和41年(1966年) 参加10チーム
発足以来初めて入れ換えチームなしの10チーム3回総当り、優勝はスリッカーズが2年連続優勝。
この年の大きなできごとは、故小川半次衆議院議員を名誉会長に迎えたことであろう。
ご本人も何度か我々の月例会や 後の10周年記念の開会式にも短時間ながらご出席いただいた。
★昭和41年とは‥
高校野球では 中京商業が春夏連覇を果たし、プロ野球は ジャイアンツのON時代がまさに黄金期を
迎える一方、ドラフト制が始まりドラフトによる初の新人が誕生するという歴史的なできごとがあった。
■8年目 昭和42年(1967年) 参加9チーム
このころから上位チームの実力が伯仲してきて、どこが優勝するか予想できない戦国時代へとなって
きて、一試合一試合が面白くなってきた。
一方、下位チームはついていけなくなり脱退していくことになる。比較的強力で技術研究会の流れを
くむ「西展クラブ」もそのひとつ、成績が急降下して解散してしまった。
9チーム3回戦総当りでリーグ戦を行い、実力がありながら優勝できなかった「西陣イーグルス」が
参加5年目で初優勝。
そのイーグルスも、珍記録の1インニングに満塁ホームランを2本も打たれてヤローズに大敗するなど
一歩間違えると どうなるか判らないほどであった。
■9年目 昭和43年(1968年) 参加6チーム
ついていけないチームが続出する中、6チームが残り、少数精鋭で4回総当りという史上最少参加チー
ム数でのリーグ戦となった。
しかし、リーグ存続か否かの危機感は全くといっていいほどなかった。
星のつぶし合いをする中で「青友クラブ」が初優勝した。
なお、この年、高尾潔が京都へ帰ってきたので 再び当連盟役員に復帰した。
発起人の一人が戻ってきたことは喜ばしいことであったが 高尾がいない間がんばってくれた大川勝
三が都合でチームと共に当連盟を離れていったのもこのころであり、10周年を、ひとつの転換期を迎
えていたことも事実であろう。
■10年目 昭和44年(1969年) 参加8チーム
西陣若生軟式野球連盟は発足10周年を迎えた。
開会式には、小川半次衆議院議員名誉会長の出席を仰ぎ、晴れやかなスタートとなった。
これを機会に、福島滋弥会長の英断で真紅の西陣織の大優勝旗がつくられることになった。
果たして、最初に優勝旗を手にするチームはどこか‥みんなが注目した。
8チーム3回総当りでスタートしたが 「ブロナー」が一回りしたところで脱退してしまう。
優勝は、徐々に力をつけてきたヤローズと実力派スリッカーズが14勝5敗で同率首位、
初めてのプレーオフ(優勝決定戦)が今出川球場で行われ、6:5でヤローズが劇的なサヨナラ勝ち。
ヤローズはチーム結成11年、若生リーグ参加10年目で初優勝となり、歴史的な優勝旗を手にした最
初のチームとなったのである。
また、この年から公認軟式野球ボールがA号からL号へと 硬式ボールと同じサイズになり、投手不利
打者有利が顕著に現れ、ホームラン数が激増した。
◇ホームラン数◇
昭和43年度が60試合で30本だったものが 昭和44年度は70試合で148本、約5倍というものす
ごさ。 ヤローズはチーム総計33本を放ち、この年の記録はリーグ、チームとも破られていない。
★昭和44年とは‥
人類の夢、月面散歩が実現した。 アポロ11号が人間を乗せて月面に着陸し、それを地球上の人々が
テレビの画面で見られるという歴史に残る年である。
プロ野球は花の44年組といわれる大選手豊作の年でもあった。 新人王の田淵幸一、有藤通世、その
ほか山本幸二、星野仙一、山田久志、東尾修、富田勝、金田留弘、大橋穣、高橋直樹、大島康徳など
現役から指導者になるまでその後のプロ野球を支えてきたひとたちばかりである。